くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度
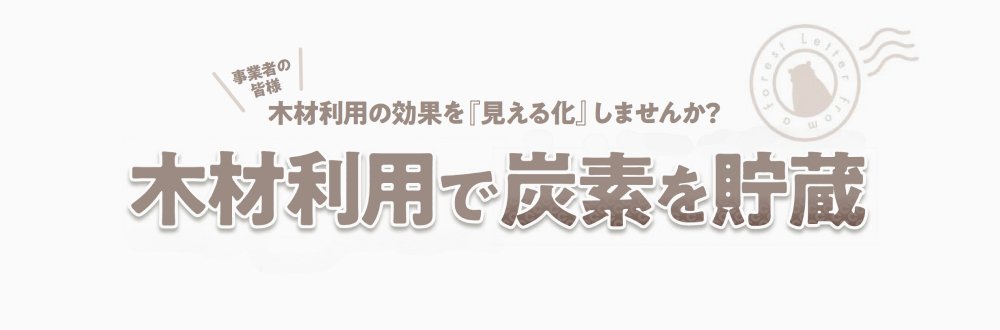
背景と目的
熊本県が令和元年12月に宣言した、「ゼロカーボン社会・くまもと」の実現に向けて、CO₂の吸収・貯蔵によるCO₂実質ゼロ化を図る取り組みが求められています。
令和3年度には、脱炭素社会の実現を目的とした「都市(まち)の木造化推進法」が施行され、木材利用を推進すべき対象が民間建築物を含む建築物一般拡大されました。
SDGsの観点からも、民間での木材利用を後押しし、誰もが気軽に取り組める制度を整備することで、木材利用の意識の醸成と脱炭素社会の実現を目指します。
制度の概要
建築物に使用された木材量から、国が制定したガイドライン(建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン)に基づき、炭素貯蔵量を県が算出し認証します。
認証した炭素貯蔵量について、建築物の施主や工務店等に「認証書」を交付し、県が公表することで、木材の炭素貯蔵量を「見える化」し、脱炭素に貢献した企業等のPRや、民間建築物における木材利用の促進につなげます。
申請方法及び申請の流れ
申請方法は以下の①~③の書類を作成のうえ、メールまたは郵送にて、県木連に提出してください。
- くまもと県産木材炭素貯蔵量認証申請書(第1号様式)
- くまもと県産木材等使用量実績証明書(第2号様式)
- 認証対象の写真(任意様式)
申請者
住宅の場合:工務店等
それ以外 :施主
過去3年以内に建築され、構造や内装・外装木質化等に県産木材が使用された住宅、事務所、商業施設等
メリット
脱炭素社会に貢献した証として対外的なPR、企業イメージの向上
- 建築物の木材使用料を確認
- 国のガイドラインに基づき炭素貯蔵量を認証
- イベント等において認証書の交付
- 認証結果は県HP等で公表
デカボナ木業とは
本制度に取組んだ企業等は、脱炭素(Decarbonization(デカボナイゼーション))社会の実現に貢献するため、建築物に県産木材を使用し炭素貯蔵に取り組む企業として、「デカボナ木業」と呼称しています。(実施要領第5条2)
申請者のイメージ
事例1:住宅の場合

| 対象施設 | 住宅戸数3件 |
|---|---|
| 県産木材使用量 | 60㎥(合計) |
| 炭素貯蔵量 | 36.4t-CO2 (一世帯当たりのCO2排出量約10年分に相当) |
事例2:住宅以外の場合

| 対象施設 | 新築校舎 |
|---|---|
| 県産木材使用量 | 138.4㎥ |
| 炭素貯蔵量 | 83.9t-CO2 (一世帯当たりのCO2排出量約22年分に相当) |
さらに、申請者が下記(1)、(2)に該当する場合、
それぞれにメリットが付与
(1)申請者が事業活動温暖化対策計画書策定者※2の場合
※2条例で、温室効果ガスの排出抑制への取組み等を県へ提出が義務化されている、①「大規模エネルギー使用事業者」又は「自動車運送事業者」、②これら以外の任意策定者
メリット
認証された炭素貯蔵量※3を、温暖化ガス排出量抑制を図るための補完的手段として、実施状況報告書における削減量への記載が可能。
※3県産木材による炭素貯蔵量のみ記載可能
参考:熊本県森林吸収量認証制度についても、補完的手段として認められている。
実績報告書の提出
「事業活動温暖化対策計画書」及び「事業活動温暖化対策実施状況報告書」の受理、県HPでの公表
(2)申請者が熊本県SDGs登録事業者の場合
メリット
SDGsの達成に向けた取組みの実績として使用することが可能。
更新申請書の提出
「熊本県SDGs登録制度」の登録及び更新事務、登録者名の県HPでの公表


